日本獣医師会雑誌の2023年11月号の「産業動物獣医療の現状と今後の展望」と題された論説の紹介のつづき。
ー
産業動物の獣医療では、
獣医師の不足、
獣医師の高齢化、
新規獣医師の参入減少、
診療効率の低下、
収支の悪化、
代替獣医師の確保の課題
が顕在化していて、特に家畜飼養頭数の少ない都府県(道は抜かれているよ!)で顕著、と書かれている。
これは異論はない。
北海道は「家畜飼養頭数の少ない都府県」から外されているが、北海道においてもマンパワーの低下は感じられる。
そして、家畜診療所収支の悪化。
人件費をかければ獣医師は雇えるし、もっと人件費をかければ雇用でも、卒後研修もできるかもしれないが、診療所勘定が赤だとそうはいかない。
15年前の平成20年度(2008年度)までNOSAI家畜診療所の診療割合は70%を超えていたが、令和3年度(2021年度)は58.6%まで低下しているのだそうだ。
グラフによれば、開業もその他(他団体、家畜保健衛生所、大学など)もシェアが増えている。
地域の開業の獣医師も高齢化し廃業してきたはずだが・・・・
家畜保健衛生所や大学がそれほど地域の大動物診療を本気で請け負っているとは思えない。
-
栃木県、東京都、大阪府、和歌山県は以前からNOSAIの家畜診療所がなく、令和5年4月からは静岡県もNOSAI家畜診療所を廃止した、とのこと。
石川県、京都府、和歌山県、島根県、徳島県、高知県、長崎県は家畜保健衛生所が家畜の診療を行っている。
「離島・中山間地等の遠隔地や、診療効率の低い地域に対して獣医療の提供と維持に多大な貢献をしている・・・」
とあるが、現実には毎日往診して診療しているとは思えない。
数日おきの診察と置き薬の配布がせいぜいではないだろうか。
(実際とちがっていたら御免なさい。あくまで私の推測です)
-
私はNOSAI職員として働いてきたので、「先生のところは国営診療所だから」と言われることがある。
たしかに、家畜共済は国の法律に基づいて運営されているし、私が働いているのはNOSAIの直営診療所だが、倒産することのない国営や地方自治体所有とはちがう。
経営が成り立たなくなれば、人は雇えなくなるし、廃止・撤退・倒産しうる。
全国的には、以前から無”獣医”地域はあったのだし、それは広がりつつある。
北海道は家畜の頭数が多いので、NOSAI直営診療所がシェアを占めてきたが、それも厳しくなっている。
NOSAI北海道はあまりに広域化、大規模化されすぎて、経営・運営はとても難しくなった。
経営感覚、コスト意識が薄れれば、NOSAI北海道の直営診療所もたちまち成り立たなくなるだろう。
ー
この著者は、「産業動物診療の未来を考える」として、
(1)獣医師の雇用確保
・新卒の雇用
・中途採用の雇用
(2)職場環境の整備
(3)遠隔診療
を挙げておられる。
「展望」ではあるかもしれないが、未来への提言としては私はこころもとないと感じる。
それは著者自身も感じておられるのではないだろうか・・・・
-
私は北海道で大動物診療に身を置きながら、全国のこういう牛の診療の現状についてまとめたデータを知らなかった。
多くの獣医さんや牧場、農場の方もそうではないだろうか。
まず現状を知って、それぞれの立場で将来への展望と、建設的な方策を考えていただきたい。
/////////
ゆうべは雪もちらついた。
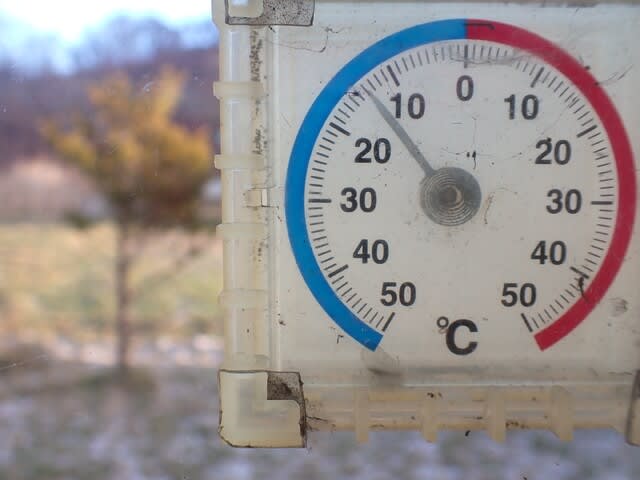
今朝は冷え込んでいた。
ゆうべは人工流産させ胎仔を引っ張りださなければならなかった。
今朝は、ひどい外傷の急患に、疝痛の開腹手術。
突然寒くなって人も馬も堪えるのかも。